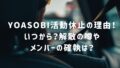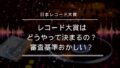みなさん、年末になるとテレビで放送される日本レコード大賞。
かつては、その年の音楽シーンを代表する晴れやかな授賞式でしたが、
近年は「やらせではないか?」という声をよく耳にしますよね。
実は、この疑惑には長い歴史があるんです。
今回は、日本レコード大賞の「やらせ疑惑」について、詳しく見ていきましょう。
レコード大賞「やらせ」と言われる3つ理由
かつては「レコード」や「CD」の売上が音楽の人気を測る重要な指標でしたが、今はストリーミングサービスやYouTubeなど、音楽の楽しみ方が多様化しています。
大衆の支持を反映しているように見えないため、
「レコード大賞はやらせ」という疑問が生まれるのも無理はありません。
レコード大賞「やらせ」と言われる3つ理由見ていきましょう。
レコード大賞やらせ理由1. 売上と受賞の不一致
レコード大賞の選考結果と、実際の音楽市場での人気に「ズレ」があるのではないか?という指摘も多いんです。
CDの売上枚数や配信数が上位なのに受賞できない、逆に、あまり知られていない曲が受賞するというケースが度々あります。
最近では、2023年にYOASOBIの「アイドル」が年間チャート1位を獲得したにもかかわらず、優秀作品賞にノミネートすらされなかったことが大きな話題になりました。
逆に、一般的な知名度があまり高くないアーティストが受賞するケースもあり、「本当に大衆の支持を反映しているのか?」という疑問の声が上がっています。
特に近年は、ストリーミング配信の普及で音楽の楽しみ方が変化している中、従来の評価基準との間にギャップが生じているようです。
レコード大賞やらせ理由2. 授賞式出席が必須?
「授賞式に出られないアーティストは選考対象外」という噂も根強くあります。
実際、YOASOBIやAdoなど、テレビ出演を控えめにしているアーティストが選考から外れているケースが見受けられるんです。
これって、本当に音楽の評価だけで決まっているんでしょうか?
視聴率重視のテレビ番組としての側面が、純粋な音楽賞としての評価を歪めているのではないか、という指摘も。
テレビ局と音楽業界の関係性が、選考に影響を与えているのではないかという疑念も持たれています。
レコード大賞やらせ理由3. 選考基準の不透明さ
レコード大賞の選考基準には「大衆の強い支持を得た作品」という項目がありますが、具体的にどのように判断しているのか、その基準は明確にされていないんです。
CDの売上?配信回数?SNSでの反響?
様々な指標がある中で、何を重視しているのかが見えにくいんです。
また、選考委員の構成も、果たして現代の音楽シーンを適切に評価できているのか疑問視する声も。
この不透明さが、様々な憶測や疑惑を生む原因になっているという指摘も少なくありません。
レコード大賞「やらせ」はいつから疑惑が?
実は、レコード大賞への疑念は1980年代から存在していました。
1987年、近藤真彦さんの「愚か者」が年間売上上位ではなかったにもかかわらずレコード大賞を受賞。この時から、ジャニーズ事務所への忖度ではないかという声が上がっていたんです。
その後も疑惑は途切れることなく続き、2000年代に入ってからSNSが普及すると、「やらせではないか」という声はさらに大きくなっていきました。
レコード大賞「やらせ」疑惑があるアーティストたち
1987年:近藤真彦「愚か者」
レコード大賞の「やらせ疑惑」の発端となったのが、この近藤真彦さんの受賞でした。
「愚か者」は、年間売上ランキングで上位に入っていなかったにもかかわらず、大賞を受賞。
このとき初めて、ジャニーズ事務所の影響力の大きさが取り沙汰されることになります。
音楽業界では、この頃から「忖度」という言葉が使われ始めたんです。
この受賞をきっかけに、レコード大賞の選考基準に対する疑問の声が上がり始めました。
1989年:光GENJI「パラダイス銀河」
光GENJIの受賞は、ジャニーズ事務所の影響力に再び注目が集まるきっかけとなりました。
特に、年末の番組出演との関連性を指摘する声が多く上がったんです。
当時、光GENJIは年末の音楽番組の目玉として注目されており、「テレビ局の意向が働いているのでは?」という声も。
この頃から、レコード大賞とテレビ局の関係性にも疑問が投げかけられるようになりました。
1995年:TRF「寒い夜だから…」
TRFの受賞で特に話題になったのが、エイベックス所属アーティストの優遇説です。
当時、エイベックスは音楽シーンで急速に台頭してきた新興勢力。
この受賞を機に、「視聴率重視の選考なのでは?」という指摘が相次ぎました。
若者に人気のダンス音楽を前面に押し出したTRFの選出は、従来の演歌や歌謡曲とは異なる新しい潮流を象徴する出来事でもありました。
1999年:GLAY「Winter, again」
GLAYの受賞は、大手レコード会社の影響力に注目が集まるケースでした。
確かに「Winter, again」は大ヒット曲でしたが、
「音楽性よりも商業的な成功が重視されているのでは?」という指摘も。
バンドブームの象徴的存在だったGLAYの受賞は、レコード大賞の選考が時代の流れに影響されているのではないか、という新たな議論を呼ぶことになりました。
2005年:つボイノリオ「蝶々」
この受賞は、多くの人を驚かせました。
つボイノリオさんの知名度と受賞のギャップが大きく話題に。
ちょうどこの頃、インターネットが普及し始めた時期で、ネット上では「誰?」「なぜ?」という声が多数上がりました。
実は良曲だったという評価もありますが、一般視聴者との認識の違いが、SNSによって可視化された初期の例と言えるでしょう。
2009年:嵐「僕の見ている風景」
嵐の受賞でジャニーズ事務所への忖度説が再び浮上。
特にこの年は、TwitterなどのSNSが普及し始めた時期で、批判の声がこれまで以上に可視化されました。
ただし、嵐は当時、国民的アイドルとして確かな人気を誇っていたため、「実力と事務所の影響力、どちらが決め手だったのか」という議論を呼ぶことになりました。
2016-2017年:AKB48系列
AKB48グループの2年連続受賞は、様々な議論を呼びました。
特に、CDの売り方に対する疑問の声が大きく、握手券付きCDによる売上の是非が問われることに。
48グループの影響力は確かに大きかったものの、「純粋な音楽性による評価なのか」という疑問が渦巻きました。この頃から、CDの売上至上主義への批判も高まっていきました。
2022年:Da-iCE
Da-iCEの受賞は、また新たな議論を呼び起こしました。
確かに実力派グループとして知られていましたが、一般的な知名度との間にギャップがあると指摘されたんです。
特に、ストリーミング全盛時代における評価基準の在り方について、改めて問題提起されることになりました。
「CDの売上だけでなく、配信数も含めた新しい評価方法が必要なのでは?」という声も多く上がりました。
2023年:BE:FIRST
この年の受賞で特に話題になったのが、「YOASOBI」や「Ado」といった人気アーティストのノミネート外れ。
BE:FIRSTの受賞自体は実力を評価する声も多かったものの、「なぜあの人気アーティストがノミネートすらされないのか?」という疑問が噴出しました。
テレビ出演との関連性を指摘する声も多く、新しい音楽消費形態と従来の選考基準との不一致が、改めてクローズアップされることになりました。
エイベックス優遇説も
興味深いのは、過去20年間でエイベックス関連会社のアーティストが14回もレコード大賞を受賞しているという事実。
これを見ると、
「特定のレコード会社が優遇されているのでは?」
という疑問も納得できますよね。
レコード大賞「やらせ」の原因は時代と選考基準があってないから?
実は、レコード大賞を取り巻く環境も大きく変化しています。
1959年の創設から1970年代までは、その名の通り「レコードの売上実績」が最重要視されていました。この時期は、音楽業界関係者が選考委員の中心となり、アーティストの知名度や人気も重要な判断材料。まさに、「売れた歌手が評価される」時代だったんです。
ところが1980年代に入ると、単なる売上だけでなく「芸術性」や「独創性」といった要素も重視されるようになります。特筆すべきは、「その年を代表する作品」という新しい観点が加わったこと。また、この頃からテレビ局関係者も選考に関与するようになり、より幅広い視点での評価が行われるようになりました。
そして1990年代以降は、さらに複合的な評価へと進化。現在の選考基準は、大きく5つの要素で構成されています。まず基本となるのが、作曲、作詞、編曲を通じた芸術性。そして、独創性や企画性の高さ、歌手の歌唱力も重要な判断材料です。さらに、大衆からの支持も欠かせない要素として挙げられています。
特に注目すべきは「その年度を代表する作品性」という基準。
これは、単なるヒット曲というだけでなく、その年の音楽シーンや時代性を象徴する楽曲であることも求められるようになったということです。このように、レコード大賞の選考基準は、音楽産業や社会の変化に合わせて、より多面的な評価を行うように変化してきたのです。
この変わり用に「レコード大賞はやらせ」と言われてしまう原因の1つかもしれません。
レコード大賞はやらせ!?いつから?疑惑まとめ
レコード大賞は確かに長年の歴史を持つ権威ある音楽賞ですが、時代とともに変化する音楽シーンに追いついていない部分があるのかもしれません。
選考基準の透明化や、現代の音楽消費スタイルに合わせた評価方法の導入など、何らかの改革が必要な時期に来ているのではないでしょうか。
ただし、これらの「やらせ疑惑」の多くは、確定的な証拠があるわけではありません。
むしろ、不透明な選考過程や時代にそぐわない運営方法が、様々な憶測を生んでいるとも考えられます。
大切なのは、アーティストたちの努力と才能を正当に評価できる賞として、レコード大賞が生まれ変わることではないのかなって感じます。
視聴者である私たちも、単に「やらせだ」と決めつけるのではなく、どうすれば日本の音楽シーンをより良くできるのか、考えていく必要がありそうですね。